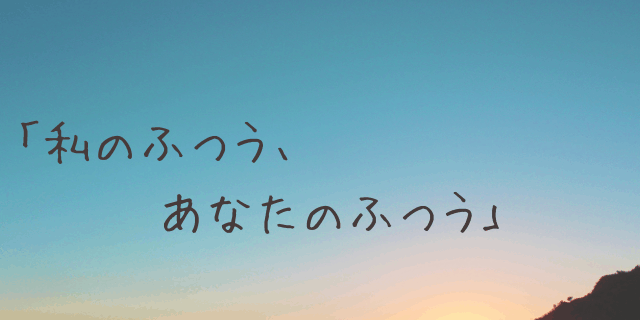「あら、上手に箸持てるのね?」
「へぇ、器用にハサミ使うもんだね」

子どもが生まれようとする時の、ただただ無事に生まれてくれさえすればと思っていた気持ちはどこへやら、その子が成長するに従って、あれこれと欲をかいて注文をつけるようになる。そろそろ歩けるようになるだろうか、もう言葉を話してもいい頃だ、近々、箸や鉛筆の持ち方、ハサミの使い方等も教えなければ…。
根底には、よその子と比べてうちの子は「ふつう」の範疇から逸脱してはいないだろうかという心配がある。親戚のあの子は◇カ月で歩き始めた、隣の家のあの子は△歳で箸が使えるようになった、等々、つい周りと比べてしまう。早い分には鼻高々であるが、遅いとなればそれが心配の種となる。「うちの子は『ふつう』だろうか…?」 そもそも何をもって「ふつう」というのかは大変あいまいである。強いて言うならば、「みんなと同じ」ということであろうか。
浄土に咲く蓮の花は、「青色青光、黄色黄光、赤色赤光、白色白光」(『仏説阿弥陀経』)といわれ、それぞれが違った色のままに、光かがやいている。「みんなと同じ」だから正しい、というものでもないし、ましてやそれをもって「ふつう」であると考えるのはただの幻想である。本来、誰しもが個別の存在であって、私たちがつい考えてしまう「ふつう」などというものは存在しない。

「みんな」の意見や評価に飲み込まれて、自己や他者の本来性を無視して「ふつう」を押し付ける在り方になってはいないかと、振り返りが欠かせない日々である。
ところで、冒頭の2つの「 」は、私が昔よく言われ、場合によっては成人を過ぎてからも言われた言葉である。左利きの私が、左手で箸を持ち、ハサミを使うことは、私にとってはふつうのことであるのだが。
『Network9(2022年9月号)より引用』田上 翼(茨城1組 一乘寺)