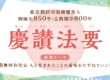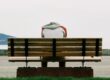『「仏説」としての「煩悩具足の凡夫」』
我々人間は、どうして「我々は…」という感じ方をするのだろうか。野球のWBCの試合を観戦していたとき、どうしても、「日本」を応援したくなる自分がいた。相撲や卓球の試合を見ていても、別に贔屓にする選手がいるわけでもないのに、観戦していて、知らず知らずのうちに、必ずどちらかを応援している自分に気付いた。そして、人間はどうして、自分に親和性を感じる人間と、そうでない人間を分けてしまうのだろうかとも思った。これは気がつけば、そうしている自分に眼がいくので、「知らず知らずのうちに」だから根が深い。
親鸞ならば、「仏かねてしろしめして、煩悩具足の凡夫とおおせられたること(『歎異抄』第九条)と言うかもしれない。「煩悩具足の凡夫」とは、阿弥陀さんのみがご存じのことであり、それが「おおせ(仰せ=教え=仏説)」という意味だ。これは「おおせ」だから、あくまでも阿弥陀さんが、我々に呼びかけられる言葉であって、それを「自分のこと」だと、平然と受け止めたら大間違いだ。人間が、「自分のこと」として受け止められるのは、自分が理解した範囲内のことだけだ。その理解も、「劣等感」の受け止めだ。「自分は『煩悩具足の凡夫』だから、どうしようもない者なのだ」と、「劣等感」で受け止め、さらに、「自分は『煩悩具足の凡夫』だけれども、それは仕方がないのだ」と自己慰撫する。そこに阿弥陀さんはいない。自分で自分のことを、あれこれと斟酌しているに過ぎない。
だから、阿弥陀さんは、決して「劣等感」で受け止められないように、「おおせ(仏説)」とされたのだ。「おおせ」とは、外部からの声であり、自己の内部のことと受け止めてはならないという常則である。常に、「万劫の初事」として聞く言葉であり、決して人間が「分かった」と「既知」の内部にならないものだ。つまり、「自己」とは、自分にとって、永遠に不可思議な出来事なのだ。
親鸞も、「煩悩具足の凡夫よ」と呼ばれ続けたのだろう。そのとき親鸞は、「悲しきかな、愚禿鸞」(『教行信証』信巻)と受け止めると同時に、「ああ、弘誓の強縁、多生にも値いがたく」(『教行信証』総序)と、思わず叫んだのだろう。この、「悲しきかな」と「ああ(噫)」を連動して引き起こすものが「仏説」である。
煩悩を自覚して、「悲しきかな」と悲嘆した途端に、煩悩が私を教える〈教材〉に転換する。煩悩が起こる度に、阿弥陀さんから具体的な〈教材〉が与えられる。 それは、一生を貫く〈私一人〉への有り難い〈教え〉だ。だから親鸞は「ああ(噫)」と叫ばざるを得なかった。そもそもそれは、阿弥陀さんから〈私一人〉への、直々のプレゼントなのだから。
東京6組 因速寺 武田 定光 師『東京教報』 185号 巻頭言(2023年10月号)